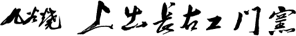Collections(カテゴリ)
-

干支「午年」
馬と人間のつきあいは古く、紀元前4300年頃まで遡ることができます。重い荷物を運び、遠くへ人を乗せ、田畑を耕し、戦いの場所に立つ。まさに馬は人間の暮らしを支える大切な存在でした。これまで描かれてきた多くの図像が、馬具を身に纏った姿で描かれていることからも、馬が担ってきた役割を知ることができます。 馬は人の感情を読み取る力があるそうですが、人間との深い関係を築けた要因のひとつとして「馬銜(はみ)」という道具の存在があります。馬の口には、前歯と奥間の間に「歯槽間縁(しそうかんえん)」と呼ばれる歯のない部分があり、その隙間に棒状の馬銜を通しその両端に手綱をつなぐことで、人間の意思や合図を正確に伝えることできました。つまり、この歯槽間縁の発見と、馬銜の発明が「人馬一体」と呼ばれるほどに私たちの距離を縮めたのです。もっとも馬からすれば大迷惑な話だったかもしれませんが。
-

干支「巳年」
私たちにとって、四肢のない蛇は外見的には不気味な存在かもしれませんが、古代から世界各地で宿仰の対象とされてきました。脱皮を繰り返すことから「再生」や「生命力」の象徴とされ、自らの尾を喰み環状になった「ウロボロス」の図案は「永遠」を意味し、さまざまな宗教でシンボルとして用いられてきました。日本では、蛇は害獣であるねずみを捕食することで穀物を守り、財宝の女神である弁オ天の使いともされています。とりわけ白蛇は「幸運」や「清浄」の象徴として広く知られています。また、お正月には欠かせない鏡餅や注連縄も蛇の姿を模したものとされ、蛇を神聖な存在と見なした日本人の感性が今でも強く残っています。